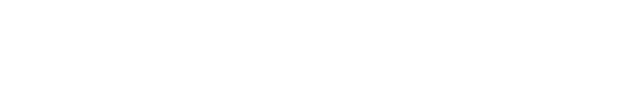嘔吐・下痢
嘔吐・下痢について
よくある症状ですが、注意が必要です
嘔吐や下痢は、小児科でよくみられる症状のひとつです。
それでもお子さんが急に吐いたり、下痢をしたりすると、ご家族はとても心配になりますね。
これらの症状が続くと、体の水分が失われて脱水につながることがあるため注意が必要です。
嘔吐や下痢の原因
ウイルス性胃腸炎がほとんどです
嘔吐や下痢の多くは、ウイルス性の胃腸炎が原因です。いわゆる「胃腸かぜ」ともいいます。
さまざまなウイルスが胃腸炎を起こしますが、中でもロタウイルスによるものは、重症な下痢により脱水を起こしやすく、特に注意が必要です。
他にも次のような病気のこともあります
- 細菌性胃腸炎
- 尿路感染症、肺炎、中耳炎、髄膜炎など
- 炎症性腸疾患
- 腸重積や虫垂炎
- 抗菌薬起因性下痢
大腸菌やサルモネラなどによる細菌性胃腸炎では、40℃以上の高熱、血便、強い腹痛、意識障害などを伴うことがあります。
胃腸炎のほかにも、尿路感染症、肺炎、急性中耳炎、髄膜炎などの感染症や、炎症性腸疾患のほか、腸重積、虫垂炎などの外科的な病気でも嘔吐や下痢がみられることがあります。
また、乳幼児に抗菌薬を投与した場合に、腸内細菌叢の乱れから下痢を起こすこともよくみられます。
食中毒
食中毒とは、食品に含まれる細菌やウイルス、毒素などを食べることで起こる急性の健康被害のことをいいます。
食中毒でも嘔吐、下痢、腹痛などがよくみられます。
溢乳・咳あげ
生後6か月ごろまでの乳児では、「溢乳(いつにゅう)」といって、哺乳後に母乳やミルクが逆流して溢れ出ることがよくあります。これは生理的な現象で、成長とともにみられなくなっていきます。
また幼児では激しく泣いたり、咳き込んだときに吐いてしまうことがあります。
いずれも、吐いたあともケロッとしていて、吐き気や腹痛がない、繰り返し吐いて悪化しないようであれば、心配ありません。
注意が必要な症状
すぐに受診しましょう
次の症状がある場合は、ウイルス性胃腸炎ではない他の病気によることがあります。
- 生後3か月未満の発熱
- 39℃以上の高熱
- 息切れや多呼吸
- 意識障害、ぐったりして元気がない
- 胆汁性嘔吐(黄色や緑色の吐物)
- 血性嘔吐
- 強い腹痛
- 血便、真っ黒の便
これらの症状がある場合は、すぐに小児科を受診してください。
脱水症について
嘔吐・下痢が続くと、体の水分と塩分が失われ、脱水になることがあります
- ぐったりして元気がない
- 喉が渇いて、水を欲しがる
- 多呼吸
- 皮膚にハリがない
- 皮膚をつまんですぐに戻らない
- 手足が冷たい、指先の色が悪い
- 目がくぼみ、げっそりする
- 口や舌が乾燥する、涙が出ない
- 尿の量が少ない
これらは脱水が進行している兆候です。
すぐに受診しましょう。
ご家庭での療養について
なにを飲ませたらいいの?
- 嘔吐や下痢があるときは、糖分と塩分がバランスよく含まれた飲みものが最適です。
- そのためには、経口補水液(OS-1など)が理想的です。
- 飲みにくい場合は、リンゴジュースや具のない味噌汁やスープも良いでしょう。
- 経口補水液がないときは、ご家庭で作ることもできます。
水 1ℓ + 砂糖 20g + 食塩 3g
- さらに柑橘系の果汁を加えると飲みやすくなります
- 授乳中の赤ちゃんには、母乳やミルクを飲ませます。1口ずつ、5〜10分おきに与えてください。ミルクは薄めずに飲ませてください。
*お茶や水だけにすることは避けましょう。
*スポーツ飲料は、糖分と塩分のバランスが最適とはいえないため、少量にしてください。
経口補水と食事の実際
補水開始期
- 吐き気が強いときは、1〜2時間ほどお腹を休ませましょう。
- 吐き気がやや落ち着いてきたら、経口補水を開始します。
- まず、ティースプーン1杯(5ml)の量を、5〜10分おきに与えてください。
- 吐かなければ、少しずつ量を増やしましょう。
- 一度にごくごく飲ませないように、1回量は1〜3口程度にします。
[目標]
最初の4時間で次の量を飲ませましょう
体重(kg)× 50〜100 ml
[例えば]
体重10kgの場合:4時間で 500〜1000 ml
[参考として]
5ml を5分ごとに与えると
1時間で 60 ml になります
補水維持期
4時間以後は、下痢や嘔吐があったらその都度、追加で経口補水を行います。
目安は
- 体重 5〜9kg :1回 60〜120 ml
- 体重 10kg以上:1回 120〜240 ml
嘔吐がなくても、1日3回以上の下痢があるときは、維持期の経口補水を始めましょう。
食事開始期
吐き気がおさまり、本人が食べたがるようになれば、お粥や温かいうどんなどの食事を開始します。
食事内容の制限はありませんが、甘すぎるもの、脂っこいもの、刺激の強いものは控えた方がよいでしょう。
感染を広げないために
ウイルス性胃腸炎は、吐物や便中のウイルスが、手から口へと感染が広がります。
なかでもロタウイルスやノロウイルスは、石鹸やアルコールでは消毒が不十分なことがあります。
流水での手洗いの徹底が、最も基本的かつ効果的です。
吐物・汚染物の処理のポイント
汚染された衣類や場所の消毒には次亜塩素酸(ミルトンやハイター)が有効です。
- マスクと手袋をつける
- 吐物の上にキッチンペーパーなどを広くかける
- 次亜塩素酸ナトリウムを上からかけて消毒
- ペーパーごと吐物を拭き取って、ビニール袋に入れる
- 手袋とマスクも袋に入れて口をしっかりしばる
- 最後に必ず手を洗う
家族や周りのみんなが、こまめにしっかりと手洗いすることが重要です。
家族内でタオルを共用しない、トイレはふたを閉めて流すなどにも気をつけましょう。
登園・登校の目安
嘔吐がおさまり、しっかり食事がとれるようになって、下痢のピークが過ぎたら、登園・登校が可能です。
ウイルスは便の中に2〜3週間は排泄されることがあります。下痢が続くあいだは、引き続きこまめな手洗いを心がけましょう。