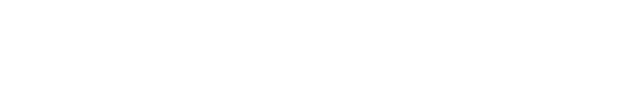胃腸炎
小児の胃腸炎について
胃腸炎は一般によくみられる病気のひとつです。胃腸炎になると、嘔吐、腹痛、下痢、発熱などの症状がみられます。原因としては、ウイルスによる感染性胃腸炎がとても多くみられます。胃腸炎では嘔吐や下痢のために脱水になりやすく、注意が必要です。
感染性胃腸炎の多くは数日で自然に回復しますが、原因によっては重症化したり、感染が広がったりすることがあるため、適切な対処が必要になります。
胃腸炎の原因
急性胃腸炎の大部分は感染性であり、なかでもウイルス性のものがほとんどです。原因のウイルスは特定できないことが多いのですが、重要なものとしてロタウイルス、ノロウイルスがあります。そのほかには腸管アデノウイルス、サポウイルスなど様々なウイルスが胃腸炎の原因となります。これらの軽症のウイルス性胃腸炎と考えられるものを「胃腸かぜ」と呼ぶことがあります。
一部には、細菌性の胃腸炎があります。代表的な原因菌は、カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌、エルシニアなどです。また海外渡航者には、コレラ菌、赤痢菌、チフス菌などの胃腸炎が起きることがあります。
その他に、赤痢アメーバやクリプトスポリジウムなどの寄生虫も感染性胃腸炎の原因となることがあります。
まれに、食物蛋白誘発性胃腸炎、好酸球性胃腸炎などの非感染性の胃腸炎もありますが、確定診断は容易ではなく、診断法や治療法も充分に確立されていません。
感染性胃腸炎の感染経路
感染経路としては、汚染された飲食物などの経口摂取や、嘔吐物や便などで汚染された手を介したり、飛沫に曝されることから感染します。
ここからは代表的な感染性胃腸炎についてみていきましょう
ロタウイルス胃腸炎
ロタウイルス感染症は、重症化しやすく、また感染力が強いことから、最も重要な感染症のひとつです。
主に冬から春にかけて流行します。
ロタウイルスが感染すると、1〜2日の潜伏期間を経て発症します。繰り返す嘔吐、水様下痢、腹痛、発熱が数日間つづき、1週間程度で自然に軽快します。
乳幼児では特に重症化しやすく、白色下痢や高熱、繰り返す嘔吐が特徴的です。重度の脱水を起こし、入院が必要になることも多くあります。合併症として、胃腸炎関連けいれん、脳症がみられることがあります。
白色下痢は、胆汁の流れに影響が出ることで白っぽい色の下痢便になるものです。ロタウイルスだけに特有のものではなく、乳幼児のウイルス性胃腸炎にはよくみられます。これらの特徴から、冬季乳児白色下痢症などと呼ばれ、ロタウイルスはその代表的な原因となります。
ロタウイルスは非常に感染力が強いことも特徴のひとつです。汚染された下痢便や吐物から、手や物を介して、あるいは飛沫から経口的に感染します。家庭内や保育施設、医療関連施設などで集団感染が起こりやすいため、注意が必要です。
感染予防には、こまめな手洗いの徹底と、吐物やおむつの処理、消毒などが大切です。
重要な対策として、生後早期の乳児に対し、ロタウイルスワクチンの定期接種が行われており、感染予防や重症化予防に効果を上げています。
ノロウイルス胃腸炎
ノロウイルスは小型の球形のウイルスで、特に冬季に感染が流行します。感染力が非常に強く、幅広い年齢層に集団感染を引き起こしますが、乳幼児の感染性胃腸炎の原因としても重要なウイルスです。
乳幼児のノロウイルス胃腸炎は、ロタウイルスと同様に重症化しやすく、症状が回復した後も便中にウイルスの排泄が長期に渡って続くことがわかっており、感染源となります。
牡蠣やシジミなどの生食や汚染された食品による食中毒としても多く、また感染者の吐物や便の飛沫、付着した手指や衣類、食器などを介して広がります。非常に感染力が強く、伝播性が高いため、家庭内や保育施設、学校、医療関連施設などで集団感染を起こす厄介なウイルスです。
感染すると半日から2日程度で発症し、嘔吐、水様下痢、腹痛、発熱が見られます。通常は数日で症状が改善しますが、下痢が長引くことがあります。乳幼児では脱水になりやすく、注意が必要です。
嘔吐物の処理には、マスクと手袋を着用し、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が必要です。処理後はしっかり手洗いを行いましょう。
細菌性胃腸炎
カンピロバクター感染症
加熱が不十分な鶏肉が主な感染源です。摂取して24〜72時間で発症し、発熱、下痢、腹痛、血便がみられます。まれにギラン・バレー症候群などの合併症を起こすことがあります。
サルモネラ感染症
鶏卵や食肉の食中毒として、さらにペット(カメや爬虫類)との接触などで感染します。潜伏期間は6〜72時間で、発熱、下痢、腹痛、嘔吐がみられます。乳幼児では菌血症を起こし重症化することもあります。急性脳症の合併にも注意する必要があります。サルモネラ菌は、症状が軽快した後も約5週間と長期に渡り、便中に排泄されます。
腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
家畜、特にウシは腸管出血性大腸菌の保菌率が高く、食肉の加工過程での汚染や、糞便に汚染された野菜や水が感染源となります。
感染すると3〜7日の潜伏期間を経て、強い腹痛と下痢で発症します。続いて血便がみられることが特徴で、重症では出血性大腸炎となります。
3〜10%に溶血性尿毒症症候群(溶血性貧血、血小板減少、急性腎不全)という重い合併症を引き起こすことがあります。腸管出血性大腸菌は感染力が強く、家庭内や保育施設などでの二次感染にも注意が必要です。
コレラ
日本国内ではほとんど見られませんが、海外渡航先で感染する可能性があります。米の研ぎ汁様の大量の水のような下痢によって、急激に脱水が進みます。清潔な飲料水と衛生的な食事管理が予防の鍵です。
細菌性赤痢
極めて感染力が強く、少量の菌でも感染します。発熱、血便、強い腹痛がみられ、幼児や高齢者では重症化のリスクがあります。
食中毒
食品に含まれる細菌やウイルス、毒素などを摂取することで起こる急性の健康被害を食中毒といいます。感染性胃腸炎の一部は、ウイルスや細菌などに汚染された食品を摂取して発症し、食中毒と分類されます。
加熱不足の肉や魚、卵、常温で放置された食品、汚染された水や生野菜などから食中毒を起こし、集団発生することもまれではありません。
特に夏場は食べ物が傷みやすく細菌が増殖しやすい環境になります。また、冬はノロウイルス感染症なども食中毒の原因となります。食品を扱う環境に常に気を配るとともに、正しい調理・保存・手洗いを心がけることが必要です。
最後に
胃腸炎は一般によくある病気で、多くの場合はウイルス性で数日で回復しますが、脱水になりやすく注意が必要です。また乳幼児では重症化しやすいことに気をつける必要があります。
高熱や強い腹痛、血便などの場合は、細菌性胃腸炎などのことがありますので、すぐに受診が必要です。
ペットの飼育や海外渡航歴、集団発生がある場合は、診断するうえで大切な情報になりますので、受診した医療機関で伝えてください。
ご家庭での対応について、「嘔吐・下痢」の項目で詳しく説明しています。ぜひこちらもご覧ください。