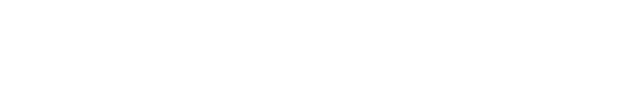予防接種を受けよう
ワクチンについて
私たちの身の周りには、細菌やウイルスなど多くの病原体が存在し、さまざまな感染症を引き起こします。これらを防ぐ最も効果的な方法がワクチン接種です。
ワクチンは、感染症の原因となるウイルスや細菌の病原性(毒性)を弱めたり失くしたりして、安全なかたちにしたものです。ワクチンを接種することで、体の中にその病気に対する抵抗力(免疫)をつくることができます。
実際に病原体が体に入ってきた場合には、その免疫が素早く反応して感染を防いだり、症状を軽くしたりすることができます。
大切なお子さまの健康を守るため、予防接種を計画的に受けましょう。
当院で接種できるワクチン
B型肝炎
定期接種
対象者
1歳未満
*B型肝炎母子感染防止対策の対象者は、定期接種の対象外となります
接種方法
【1・2回目】
4週(27日以上)の間隔をおいて2回
【3回目】
1回目の接種から20〜24週後に1回
備 考
任意で接種される場合は1回 8,800円(税込)の費用がかかります。
ロタウイルスワクチン
定期接種
ワクチン
ロタリックス(1価)
対象者
生後6週0日〜24週0日まで
接種方法
経口接種
4週(27日以上)の間隔をおいて2回
*初回は生後14週6日までに接種することが推奨されています
備 考
接種後(多くは7日以内)に腸重積症のリスクが増加する可能性が報告されています。
いちごジャムのような血便、繰り返す嘔吐、間欠的な啼泣や不機嫌などの症状がみられる場合は、速やかに医療機関を受診してください。
任意で接種される場合は1回 16,500円(税込)の費用がかかります。
*ロタテック(5価)の接種を特に希望される場合は、お電話でお申し出ください
小児用肺炎球菌ワクチン
定期接種
対象者
2か月〜5歳未満
ワクチン
15価 肺炎球菌ワクチン
20価 肺炎球菌ワクチン
接種方法
〈生後2か月〜7か月未満〉
【初回接種】
4週(27日)以上の間隔で3回
1歳までに完了
【追加接種】
60日以上の間隔で1歳以降に1回
〈生後7か月〜1歳未満〉
【初回接種】
4週(27日)以上の間隔で2回
【追加接種】
60日以上の間隔で1歳以降に1回
〈1歳〜2歳未満〉
【接 種】 60日以上の間隔で2回
〈2歳〜5歳未満〉
【接 種】 1回のみ
備 考
令和6年10月から、20価ワクチンが定期接種として使用されています。
初回接種で15価ワクチンを接種した方は、追加接種でも15価ワクチンを使用します。
15価ワクチンと20価ワクチンの交互接種は原則として不可とされています。
任意で接種される場合は1回 14,300円(税込)の費用がかかります。
5種混合
ジフテリア・破傷風・百日せき
不活化ポリオ・ヒブ
定期接種
対象者
2か月〜7歳6か月未満
接種方法
【第1期 初回】
3週(20日以上)の間隔で3回
*標準的には3〜8週間の間隔
【第1期 追加】
6か月以上の間隔で1回
備 考
任意で接種される場合は1回 22,000円(税込)の費用がかかります。
4種混合(製造販売終了)
ジフテリア・破傷風・百日せき
不活化ポリオ
定期接種
対象者
2か月〜7歳6か月未満
接種方法
【第1期 初回】
3週(20日以上)の間隔で3回
*標準的には3〜8週間の間隔
【第1期 追加】
6か月以上の間隔で1回
備 考
*2025年7月に「4種混合ワクチン」の製造販売が終了となりました。詳細についてはこちらをご覧ください
3種混合
ジフテリア・破傷風・百日せき
任意接種
任意で接種される場合は1回 7,700円(税込)の費用がかかります。
定期接種
対象者 2か月〜7歳6か月未満
接種方法
【第1期 初回】
3週(20日以上)の間隔で3回
*標準的には3〜8週間の間隔
【第1期 追加】
6か月以上の間隔で1回
備 考
*3種混合ワクチンは限定出荷となっています。直ぐに入手が困難な場合がありますので、お待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。3種混合ワクチンの接種を希望される場合は、お電話でお申し出ください
2種混合
ジフテリア・破傷風
定期接種
対象者
【第2期】 11歳〜13歳未満
接種方法
【第2期】 1回
備 考
任意で接種される場合は1回 7,700円(税込)の費用がかかります。
不活化ポリオ
任意接種
任意で接種される場合は1回 12,100円(税込)の費用がかかります。
定期接種
対象者
2か月〜7歳6か月未満
接種方法
【初回接種】
3週(20日以上)の間隔で3回
*標準的には3〜8週間の間隔
【追加接種】
6か月以上の間隔で1回
備 考
*不活化ポリオワクチンの接種を希望される場合は、お電話でお申し出ください
ヒブワクチン
定期接種
対象者
2か月〜5歳未満
接種方法
〈生後2か月〜7か月未満〉
【初回接種】
4週(27日)以上の間隔で3回
1歳までに完了
【追加接種】
7か月以上の間隔で1回
〈生後7か月〜1歳未満〉
【初回接種】
4週(27日)以上の間隔で2回
1歳までに完了
【追加接種】
7か月以上の間隔で1回
〈1歳〜5歳未満〉
【接 種】 1回のみ
備 考
任意で接種される場合は1回 11,000円(税込)の費用がかかります。
*現在、Web予約を停止しています。接種を希望される場合は、お電話でお申し出ください
BCG
定期接種
対象者
3か月〜1歳未満
接種方法
管針を用いて経皮接種 1回
備 考
接種後の経過
通常は接種後10日頃から接種部位に発赤や膨隆が生じ、化膿することもあります。
こうした変化は接種後1〜2か月頃に最も強くなり、かさぶたができてきます。
やがて3〜5か月が経つ頃には、小さな瘢痕を残すのみとなります。
まれに、接種後1〜2か月頃に脇の下などのリンパ節が腫れてくることがあります。
その場合も通常は6か月までに自然に消退しますが、気になる場合は申し出てください。
コッホ現象について
接種後1〜10日以内の早期に接種部位が赤く腫れて化膿してくる場合を、コッホ現象といいます。
コッホ現象が見られる場合は、接種前から結核に感染していたおそれがありますので、速やかに診察を受けてください。
任意で接種される場合は1回 14,300円(税込)の費用がかかります。
麻しん風しん混合
定期接種
対象者
【第1期】
1歳以上2歳未満
【第2期】
小学校就学前の1年間
5歳以上7歳未満
接種方法
【第1・2期】 各 1 回
備 考
麻しん風しん混合ワクチンのWeb予約の一時停止について
麻しん風しん混合ワクチンの供給が不安定なため、Web予約を一時停止しています。
接種をご希望の方は、お電話でお問い合わせください。
行政措置について
麻しん風しん混合ワクチンの出荷停止の影響により、接種対象期間内に定期接種を受けられないと見込まれる方に対し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種期間を延長する措置が実施されます。
対象者には市から「お知らせはがき」が発送されていますので、接種時にお持ちください。
任意で接種される場合は1回 13,200円(税込)の費用がかかります。
麻しん対策事業
任意予防接種費用助成事業
対象者
1歳以上
*定期予防接種対象者を除く
*麻しんの既往歴がない方
*麻しんの予防接種を2回接種した方を除く
抗体検査
原則として抗体価を測定し、接種の必要性を確認した後に予防接種を行う
助成回数
抗体検査 1回
予防接種 1回
助成金額
抗体検査 2,650円(本人負担なし)
麻しん風しん混合ワクチン 5,000円
自己負担額
麻しん風しん混合ワクチン 8,200円
任意予防接種費用助成事業について
風しん対策事業
任意予防接種費用助成事業
対象者
妊娠を希望する女性
その配偶者などの同居者
風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者
30歳以上50歳未満の男性
*風しん抗体検査を受けたことがある方を除く
*明らかに風しんの予防接種歴がある方を除く
*明らかに風しんの既往歴がある方を除く
抗体検査
原則として抗体価を測定し、接種の必要性を確認した後に予防接種を行う
助成回数
抗体検査 1回
予防接種 1回
助成金額
抗体検査 6,750円(本人負担なし)
麻しん風しん混合ワクチン 5,000円
自己負担額
麻しん風しん混合ワクチン 8,200円
任意予防接種費用助成事業について
おたふくかぜ
おたふくかぜ対策事業
任意予防接種費用助成事業
対象者
1歳〜小学校就学前
平成31年4月2日生まれ以降
流行性耳下腺炎の既往歴がない方
接種方法
1回目 1歳
2回目 5歳以上7歳未満
助成回数
上限 2回
助成金額
2,000円/回
自己負担額
2,400円/回
任意予防接種費用助成事業について
備 考
おたふくかぜワクチンのWeb予約の一時停止について
おたふくかぜワクチンの供給が不安定なため、Web予約を一時停止しています。
接種をご希望の方は、お電話でお問い合わせください。
助成事業外で任意接種される場合は1回 4,400円(税込)の費用がかかります。
水痘(みずぼうそう)
定期接種
対象者
1歳〜3歳未満
接種方法
3か月以上の間隔で2回
備 考
水痘生ワクチンは、おとなの帯状疱疹の予防接種にも用いられます。
任意で接種される場合は1回11,000円(税込)の費用がかかります。
日本脳炎
定期接種
対象者
【第1期】 3歳〜7歳6か月未満
【第2期】 9歳〜13歳未満
接種方法
【第1期 初回】
1週(6日)以上の間隔で2回
標準的には1〜4週間の間隔
【第1期 追加】
6か月以上の間隔で1回
標準的にはおおむね1年後
【第2期】
1回
備 考
生後6か月から3歳未満で第1期接種を希望する場合は、事前に豊田市感染症予防課・みよし市保険健康課に連絡が必要です。
特例接種について
積極的勧奨の差し控えのために接種機会を逃した方は、特例制度により公費で接種を受けることができます。
【第1・2期 特例】
平成19年4月1日生まれまでの20歳未満の方
任意で接種される場合は1回 9,350円(税込)の費用がかかります。
子宮頚がん予防(HPV)ワクチン
定期接種
対象者
小学6年生〜高校1年生に相当する女性
ワクチン
シルガード(9価)
ガーダシル(4価)
接種方法
【シルガード 2回接種】
15歳未満に初回を開始
初回、6か月後
【シルガード 3回接種】
15歳以上
初回、2か月後、初回から6か月後
【ガーダシル 3回接種】
初回、2か月後、初回から6か月後
キャッチアップ接種の経過措置
対 象
平成9年度〜平成20年度生まれの女性で、令和4年度〜令和6年度までの間に子宮頚がん予防ワクチンを1回以上接種した方
期 間
令和7年4月1日〜令和8年3月31日までの1年間
接種券
新たに令和7年度用のキャッチアップ接種券が必要です。
市に接種券の発行を申請のうえ、接種時にお持ちください。
備 考
接種後の注意
接種後に血管迷走神経反射による失神や転倒を起こす可能性があります。接種後30分程度は、背もたれのある場所に座るなどして異常がないことを確認してください。
任意で接種される場合は以下の費用がかかります。
シルガード 1回 29,700円(税込)
ガーダシル 1回 19,800円(税込)
*サーバリックス(2価)の接種を希望される場合は、お電話でお申し出ください
男性のHPV感染症
任意予防接種費用助成事業
ヒトパピローマウイルス(HPV)は男性にも感染し、中咽頭がんや肛門がん、尖圭コンジローマなどの原因になります。男性も予防接種を受けることでHPVの感染予防効果が期待できます。また性交渉による女性への感染拡大を防ぎ、子宮頚がんの予防にもつながります。
対象者
小学6年生〜高校1年生の男性
平成21年4月2日〜平成26年4月1日生まれ
ワクチン
ガーダシル(4価)
接種方法
【ガーダシル 3回接種】
初回、2か月後、初回から6か月後
助成回数
上限 3回
助成金額
16,841円/回
自己負担額
2,959円/回
任意予防接種費用助成事業について
接種を希望される場合はお電話でお問い合わせください。
新型コロナワクチン
定期接種
対象者
65歳以上
60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全による免疫の機能に障がいを有する人(身体障がい者手帳1級程度)
接種期間
10月1日〜1月31日
ワクチン
コミナティ(ファイザー)
接種方法
【追加接種】 1回
接種費用
自己負担額 4,500円
任意接種
対象者
生後6か月〜4歳
5歳〜11歳
12歳以上
接種期間
10月〜3月
ワクチン
コミナティ(ファイザー)
接種方法
〈生後6か月〜4歳〉
【初回接種】
3週(20日以上)の間隔をおいて2回
8週間後に1回
【追加接種】
3か月以上あけて1回
〈5歳〜11歳〉
【初回接種】
4週(27日以上)の間隔をおいて2回
【追加接種】
3か月以上あけて1回
〈12歳以上〉
【初回接種】
4週(27日以上)の間隔をおいて2回
【追加接種】
3か月以上あけて1回
備 考
現在、予約の受付を停止しています。
9月ごろに予約の受付を開始します。
詳細はホームページでお知らせします。
接種を希望される方はお電話でお問い合わせください。
任意で接種される場合は1回 14,300円(税込)の費用がかかります。
*他の新型コロナワクチンの接種を特にご希望される場合、対象年齢や接種スケジュール、接種量、費用などがそれぞれ異なるため、当院ではご予約をお受けできかねることがございます。あらかじめご了承ください。
インフルエンザ
定期接種
対象者
65歳以上
60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全による免疫の機能に障がいを有する人(身体障がい者手帳1級程度)
接種期間
10月1日〜1月31日
ワクチン
インフルエンザ不活化ワクチン
接種方法
皮下接種 1回
接種費用
自己負担額 1,500円
任意接種
インフルエンザ不活化ワクチン
対象者
生後6か月〜3歳未満
3歳〜13歳未満
13歳以上
接種期間
10月〜3月
接種方法
〈生後6か月〜3歳未満〉
接種量 0.25ml/回
2〜4週の間隔をおいて2回
〈3歳〜13歳未満〉
接種量 0.5 ml/回
2〜4週の間隔をおいて2回
〈13歳未満〉
接種量 0.5 ml
1回
備 考
現在、予約の受付を停止しています。
9月ごろに予約の受付を開始します。
詳細はホームページでお知らせします。
接種を希望される方はお電話でお問い合わせください。
卵アレルギーがある方でも接種は可能ですが、アナフィラキシーを起こしたことがある方は事前にご相談ください。
妊娠中に母親が接種を受けると、本人だけでなく生まれてくる赤ちゃんにもインフルエンザの発症を予防する効果を期待することができます。接種を受ける際は、念のため妊娠中であることを予診票に記入してお知らせください。
任意で接種される場合は1回 4,400円(税込)の費用がかかります。
フルミスト
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン
フルミストは鼻に噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
国内では2024/25シーズンから接種が承認されました。
痛みがなく接種でき、不活化ワクチンと同等の予防効果を期待することができます。
生ワクチンのため、免疫不全の方、免疫を抑制する治療を受けている方、妊娠中の方は接種できません。
対象者
2〜19歳未満
接種期間
10月〜3月
接種方法
左右の鼻腔内に1噴霧ずつ
合計 2噴霧 1回
備 考
現在、予約の受付を停止しています。
9月の下旬に予約の受付を開始する予定です。詳細が決まりましたらホームページでお知らせします。
接種を希望される方はお電話でお問い合わせください。
接種後の注意
接種後に鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの症状が現れることがあります。
接種後1〜2週間は、投与されたワクチンウイルスが排出される可能性があり、重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。
任意で接種される場合は1回 8,800円(税込)の費用がかかります。
高齢者用肺炎球菌ワクチン
定期接種
対象者
65歳以上
60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全による免疫の機能に障がいを有する人(身体障がい者手帳1級程度)
ワクチン
23価 肺炎球菌ワクチン
接種方法
1回
接種費用
自己負担額 2,000円
備 考
接種を希望される場合はお電話でお問い合わせください。
帯状疱疹
定期接種
高齢者用帯状疱疹
対象者
65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳
60歳以上65歳未満でヒト免疫不全による免疫の機能に障がいを有する人
ワクチン
A 水痘ワクチン
B 帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
接種方法
A 1回
B 2か月以上の間隔で2回
接種費用
A 自己負担額 3,000円
B 自己負担額 6,000円/回
帯状疱疹対策事業
任意予防接種費用助成事業
対象者
50歳以上
*定期予防接種対象者を除く
ワクチン
A 水痘ワクチン
B 帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
接種方法
A 1回
B 2か月以上の間隔で2回
助成回数
A 上限 1回
B 上限 2回
助成金額
A 4,000円
B 10,000円/回
自己負担額
A 7,000円
B 12,000円/回
任意予防接種費用助成事業について
備 考
接種を希望される場合はお電話でお問い合わせください。
助成事業外で任意接種される場合は以下の費用がかかります。
水痘ワクチン 1回 11,000円(税込)
帯状疱疹ワクチン 1回 22,000円(税込)
予防接種の実施日
実施日
月・火・金曜日
第2・4 木曜日
14:00~15:30
予約方法
予防接種は予約が必要です。
Web予約・お電話・受付窓口で承ります
- Web予約:https://takeuchi.mdja.jp
- お電話 :0565-32-1531
予防接種 当日の持ち物
忘れずにお持ちください
- 接種券(必須)
- 母子手帳(未成年は必須)
- マイナ保険証または健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 体温計
- 委任状(保護者以外の方が同伴する場合)
*接種券・母子手帳がない場合は接種できませんので、必ずお持ちください
*おたふくかぜなど任意予防接種費用助成事業を受けられる場合は、子ども医療費受給者証が必要となります
*委任状のダウンロード
おすすめの接種スケジュール
Know VPD! のおすすめ
予防接種スケジュール
0歳の予防接種スケジュール
関連リンク
Know VPD!
日本小児科学会が推奨するスケジュール
豊田市 感染症予防課 0565-34-6180
みよし市 保険健康課 0561-32-2111
ワクチンの種類
ワクチンには、大きく分けて以下の種類があります。
生ワクチン
生ワクチンは、生きたウイルスや細菌の病原性(毒性)を弱めたものです。自然感染と同じ流れで免疫がつくられるため、十分な免疫を獲得しやすいという利点があります。また、長期的に免疫力を保つために、5~10年後に追加接種が必要になることがあります。副反応としては、まれにワクチンの病原性による軽い感染症状が出ることがありますが、多くは自然に回復します。
当院で接種できる生ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- BCGワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- 水痘(みずぼうそう)ワクチン
- おたふくかぜワクチン
不活化ワクチン・トキソイド
不活化ワクチンは、ウイルスや細菌の病原性(毒性)を完全になくして、免疫をつくるのに必要な成分だけを残したものです。そのため、接種してもその病気にかかることはありませんが、1回の接種では十分な免疫を獲得できず、複数回の接種や追加接種が必要になります。
また、細菌が出す毒素(トキシン)の毒性をなくし、免疫をつくる作用だけを残したものをトキソイドといいます。不活化ワクチンとよく似た仕組みで作られたワクチンです。五種混合などに含まれるジフテリアや破傷風のワクチンは、このトキソイドにあたります。
当院で接種できる不活化ワクチン・トキソイド
- B型肝炎ワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- 5種混合・3種混合・2種混合ワクチン
- 不活化ポリオワクチン
- ヒブワクチン
- インフルエンザワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- 子宮頚がん予防(HPV)ワクチン
メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン
mRNAワクチンは、ウイルスのタンパク質をつくる遺伝情報を利用した新しいタイプのワクチンです。この遺伝情報をもとに、体内でウイルスの一部のタンパク質がつくられ、それに対する抗体ができることで免疫を獲得します。予防のために決められた回数の接種や追加接種が必要です。
当院で接種できるmRNAワクチン
- 新型コロナワクチン 「コミナティ(ファイザー)」
ワクチンを接種した後の注意
接種直後の注意
- 接種後30分ほどは院内で待機するか、すぐに連絡が取れるようにしましょう。
ごくまれにアナフィラキシー(急激なじんま疹・呼吸困難・ショック)や血管迷走神経反射(悪心・ふらつき・失神)が起こることがあります。 - お子さまの様子をよく観察し、異常があればすぐに申し出てください。
接種当日~数日間の注意
- 接種した当日は激しい運動は控えてください。
- 入浴は問題ありませんが、接種部位をこすらないようにしましょう。
よくみられる副反応
・接種部位の腫れ・赤み・痛み
通常は2~3日で治まりますが、反応が強ければ冷やしてみてください。
それでも改善しない場合は受診してください。
・発熱
小児用肺炎球菌ワクチンや新型コロナワクチンなどでは、接種当日から翌日に発熱することが比較的多くみられます。
発熱と接種部位の腫れ・赤みのほかに症状がないことがほとんどです。
熱の高さはさまざまですが、多くは1日程度で解熱します。
寒がらなければ薄着にし、脇の下などを冷やしてみてください。
高熱(38.5℃以上)の場合は解熱薬を使用してかまいません。
1日経っても熱が下がらない、他に症状がある、ぐったりしている、哺乳不良、不機嫌など心配な様子がある場合は、迷わず受診するようにしましょう。
麻しん風しん混合ワクチンなどの生ワクチンを接種した場合、数週間後に発熱や発疹などの軽い感染症状が出ることがあります。
ワクチンの役割
ワクチンには、次の大切な役割があります。
- 自分が感染しないようにすること
- 万が一感染しても、症状を軽くすること
- 周りの人にうつさないこと
1と2は、ワクチンを受ける本人を守るための役割で、「個人防衛」と呼ばれます。
3は、周囲の大切な人を守るための役割で、「社会防衛」といわれます。
もしワクチンを受けずに感染症にかかってしまったら、ときに命を失ったり後遺症を残すことも起こりえます。また、家族や友だちにうつして感染症を広めてしまうことにもつながります。ワクチンは自分のためでもあり、周りの人のためにも重要なのです。
「自分のため、そしてみんなのため」
ワクチンを接種できる人がしっかり予防接種を受けることで、地域全体で感染症の流行を防ぐことができます。
その結果、赤ちゃん・妊婦さん・高齢者・病気で免疫が弱い方などを守ることにもつながります。
ワクチンは「自分のため、そしてみんなのため」であることを忘れずに、適切に接種しましょう。
現代社会で高まる予防の大切さ
近年では、小さな子どもたちも家族でレジャー・ショッピング・外食・旅行などに出かけることが日常的になりました。また、赤ちゃんのうちから保育園などで集団生活を送る機会が増えています。そのため、感染症にかかるリスクもより高まっています。
さらに、海外との往来が活発になり、感染症が世界的に広がることがあります。2019年から世界中に広がった新型コロナウイルス(COVID-19)の大流行(パンデミック)は、その象徴的な出来事でした。こうしたことは、これからも繰り返し起こると考えられています。
子どもも大人も、みんなが適切にワクチンを接種し、必要な免疫をつけることがとても大切です。
定期接種と任意接種
予防接種には「定期接種」と「任意接種」があります。それぞれの違いと重要性について説明します。
定期接種とは?
「予防接種法」に基づき、市区町村が実施する予防接種です。費用は原則、地方自治体が負担するため無料で受けられます。
子どもの定期接種ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- 5種混合・2種混合ワクチン
- ヒブワクチン
- BCGワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- 水痘(みずぼうそう)ワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- 子宮頚がん予防(HPV)ワクチン
任意接種とは?
国が接種を認めていますが、「予防接種法」で定められていない予防接種です。費用は自己負担ですが、自治体によって助成を受けられる場合があります。
子どもの任意接種ワクチン
- 新型コロナワクチン
- インフルエンザワクチン
- おたふくかぜワクチン
など
定期接種と任意接種の違いは?
ワクチンの重要性に違いはなく、どちらも感染症を予防するために大切です。
ただし、重大な副反応が起こった場合の補償制度に違いがあります。
- 定期接種:健康被害が生じた場合、「予防接種法」に基づく健康被害救済制度による補償が受けられます。
予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 - 任意接種:補償は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
医薬品副作用被害救済制度に関する業務 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
このように、補償内容に大きな差があることを理解しておきましょう。
費用を払ってでも、任意接種のワクチンは必要?
必要です。
任意接種のワクチンも、その効果と安全性が十分に確認されているものです。
お子さまと周りのみんなの健康を守るため、ワクチンで予防できる病気はしっかり予防しましょう。
任意接種は「任意」だから不要と考えず、定期接種も任意接種もどちらも大切な予防接種であることを理解し、適切に接種することが大切です。
ワクチンの安全性
ワクチンは本当に安全?
ワクチン接種後の副反応を心配する方もいるかもしれません。しかし、ほとんどの場合、接種部位の腫れや赤み、1日程度の発熱などの軽度の反応にとどまります。
ワクチンを接種しない場合のリスクと比べると、ワクチンの副反応の方がはるかに軽いことが分かります。ワクチンを接種しないで病気にかかると、ときに命を失ったり、重い後遺症を残すリスクがあります。ワクチンの価値は、防ぐべき病気の危険性の大きさによって決まるのです。
ワクチンの安全性は世界的に認められています
ワクチンは、WHO(世界保健機関)をはじめ、世界中で推進されている最も効果的な予防手段です。ワクチンほど多くの人に使用され、接種後の安全性調査が徹底されている医薬品は他にありません。特に欧米では、科学的な研究を通じて、その安全性が証明されています。
ワクチン接種後の体調変化について
本当にワクチンが原因?
ワクチン接種後に高熱を出したり、脳炎を発症したという報道を目にすることがあります。しかし、ワクチンが直接の原因とは限りません。たとえば、接種後にたまたま風邪をひいて発熱することもよくあります。
過去に「三種混合ワクチンが脳障害を引き起こすのではないか」と疑われたことがありましたが、米国や日本で行われた調査の結果、ワクチン接種の有無による脳障害の発生率に差はないことがわかっています。このように、ワクチンと病気の因果関係が証明されていないケースが多いのです。
現在もさまざまな研究が行われていますが、ワクチンが直接の原因と断定できる重大な副反応はほとんどありません。接種部位の赤み・腫れと、接種直後のアナフィラキシーを除き、その原因がワクチンによるかどうかは、医師でも判断が難しいのです。
ワクチン接種に注意が必要なケース
以下の場合は、ワクチン接種の可否について医師と相談が必要です。
- ワクチンの成分に対して強いアレルギー(アナフィラキシー)がある場合は、そのワクチンを接種できません。
- 重度のアレルギー体質がある場合は、主治医に相談してください。
- 先天性免疫不全症や小児がん治療などで免疫抑制剤を使用している場合も、医師の判断が必要です。
これらのケース以外では、ワクチンは基本的に安全に接種できます。
複数のワクチンを同時に接種しても大丈夫?
一度に複数のワクチンを同時に接種すると、お子さんが泣いてしまうこともあり、心配になるかもしれません。しかし、同時接種には次のような大きなメリットがあります。
- 短期間で複数の病気に対する免疫を獲得できる
- 接種スケジュールがシンプルになり、打ち忘れを防げる
また、万が一ワクチンを接種する前にその感染症にかかってしまうと、重症化するリスクがあります。同時接種に不安がある場合は、医師に相談しながら進めていきましょう。
ワクチンの副反応について
ワクチンの副反応にはどんなものがあるの?
ワクチン接種後に起こる副反応には、接種部位の腫れや発熱などの軽いものと、まれに起こるアナフィラキシーや脳炎・脳症などの重い副反応があります。
副反応の多くは軽度で、一時的なものですが、まれに重大な副反応が起こることもあります。しかし、これらの症状が本当にワクチンによって引き起こされたのかは、慎重に判断する必要があります。実際には、ワクチン接種後に偶然発症した「紛れ込み」のケースも多いとされています。
ワクチンの副反応
ワクチンには病原体の成分や、免疫を活性化させる成分が含まれています。そのため、体が反応して一時的に炎症やアレルギー症状を起こすことがあります。
どのワクチンでも共通して起こりやすい副反応
- 接種部位の腫れ・赤み・痛み
- 発熱
まれに起こる重大な副反応
- アナフィラキシー(急性のアレルギー反応)
- 脳炎・脳症
生ワクチンによって起こる副反応
生ワクチンは、毒性を弱めた生きた病原体を使用しているため、軽い感染症の症状が出ることがあります。
- 麻しん風しん混合ワクチンでは、1~2週間後に発熱や発疹が出ることがあります。ただし自然感染した場合に比べて症状は軽度です。
- おたふくかぜワクチンでは、2~3週間後に発熱や耳下腺の腫れが起きることがあります。通常は軽微で自然に治まります。また、ごくまれに無菌性髄膜炎や脳炎を発症することがありますが、自然感染に比べると発症率は低く、症状も軽く済むことがほとんどです。
免疫反応との関連が疑われる副反応
- ギラン・バレー症候群
- 血小板減少性紫斑病
副反応と有害事象の違い
ワクチン接種後に起こる症状は「副反応」と「有害事象」に分類されます。
- 副反応:
ワクチンが原因で生じる、免疫形成以外の反応 - 有害事象:
ワクチン接種後に起こったあらゆる好ましくない出来事
因果関係が不明なものも含む
ワクチンを接種した後に、別の病気や事故によって発熱や嘔吐が起こることもあり、これらも有害事象として記録されます。
たとえば、ワクチン接種後に
- 別の病気にかかって熱が出た
- 食べ物が原因で嘔吐した
- 転んでケガをした
これらも「有害事象」として報告されますが、ワクチンとの因果関係があるとは限りません。
副反応を見逃さないために、すべての情報を集めて慎重に調査が行われます。しかし、ニュースでは「副反応」と「有害事象」が明確に区別されずに報道されることがあり、誤解を招くことがあります。冷静に情報を判断することが大切です。
おとなのワクチン
思春期・青年期(10~20代)
思春期以降にかかると重症になりやすい病気を防ぐワクチン
思春期・青年期に感染しやすいもの
- 子宮頚がん予防(HPV)ワクチン
- B型肝炎ワクチン
思春期以降にかかると重症化するもの
- 麻しん風しん混合ワクチン
- 水痘(みずぼうそう)ワクチン
- おたふくかぜワクチン
- インフルエンザワクチン
- 日本脳炎ワクチン
予防接種の免疫力が弱くなっているもの
- 3種混合ワクチン(とくに百日咳・破傷風)
子育て世代
赤ちゃんや妊婦さんが重症になりやすい病気を防ぐワクチン
妊娠中にかかると重症化するもの
- 麻しん風しん混合ワクチン
- 水痘(みずぼうそう)ワクチン
- おたふくかぜワクチン
妊娠中のワクチン接種で赤ちゃんがかかりにくくなるもの
- インフルエンザワクチン
- 3種混合ワクチン(とくに百日咳)
- RSウイルスワクチン
夫婦・家族間で感染しやすいもの
- B型肝炎ワクチン
予防接種の免疫力が弱くなっているもの
- 日本脳炎ワクチン
- 3種混合または2種混合ワクチン(とくに破傷風)
現役・ミドル世代(40~50代)
免疫力が低下してかかりやすくなる病気を防ぐワクチン
感染しやすいもの
- インフルエンザワクチン
- 帯状疱疹ワクチン
妊娠中にかかると重症化するもの
- 麻しん風しん混合ワクチン(特に風しん)
予防接種の免疫力が弱くなっているもの
- 3種混合ワクチン(とくに百日咳・破傷風)
- 日本脳炎ワクチン
夫婦・家族間で感染しやすいもの
- B型肝炎ワクチン
大人がかかると重症化するもの
- 麻しん風しん混合ワクチン(特に麻しん)
- 水痘(みずぼうそう)ワクチン
- おたふくかぜワクチン
シニア世代(60代~)
健康や生活にかかわる病気を防ぐワクチン
シニア世代が注意すべきもの
- インフルエンザワクチン
- 高齢者用肺炎球菌ワクチン
- 新型コロナワクチン
体力・免疫力の低下でかかりやすいもの
- 3種混合ワクチン(特に百日咳・破傷風)
- 日本脳炎ワクチン
- 帯状疱疹ワクチン
夫婦・家族間で感染しやすいもの
- B型肝炎ワクチン